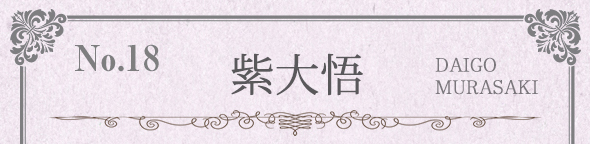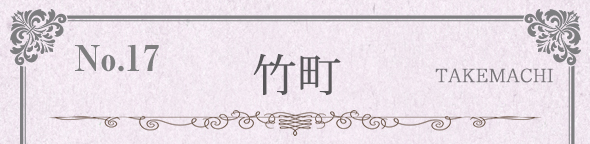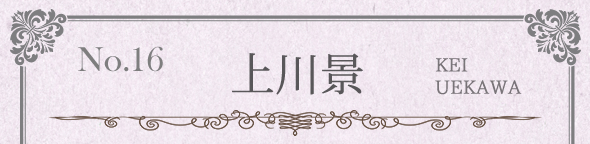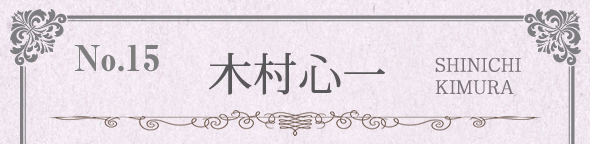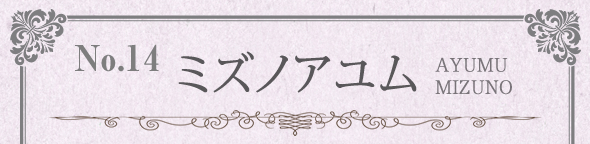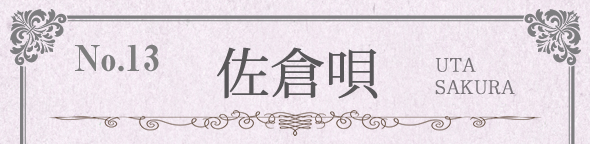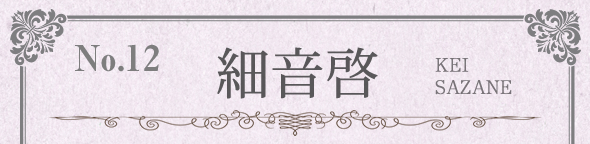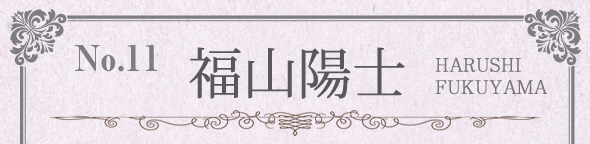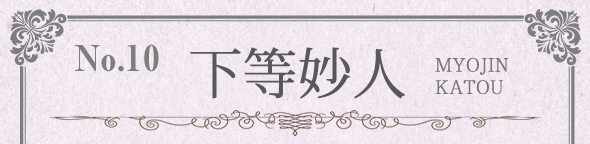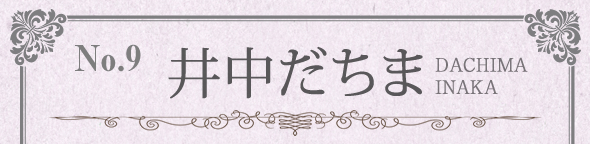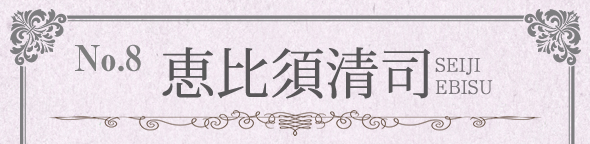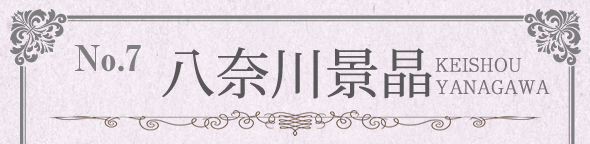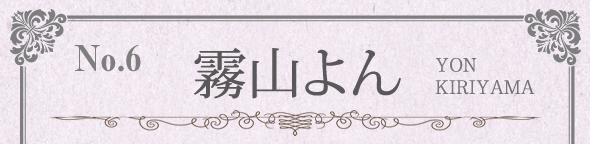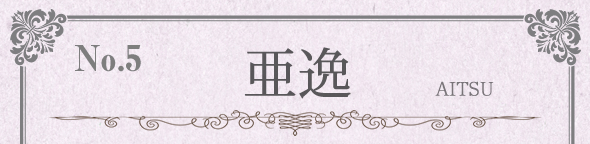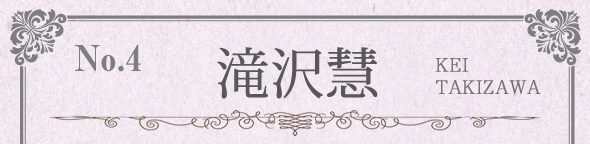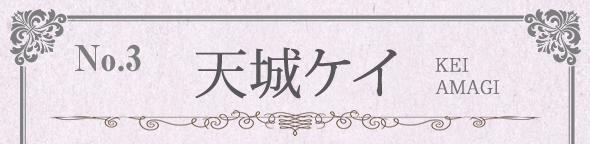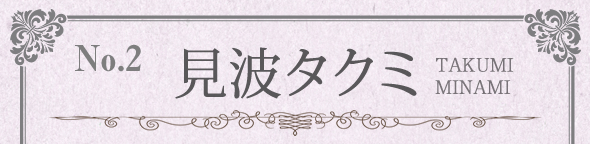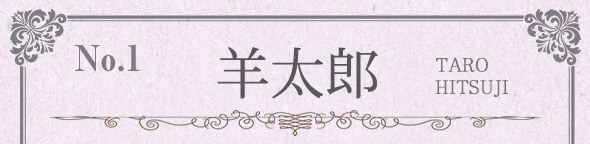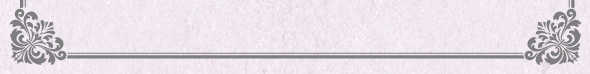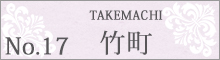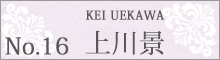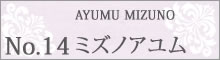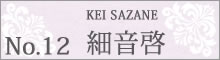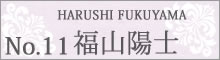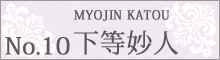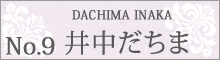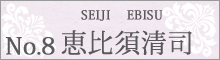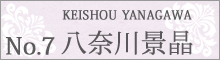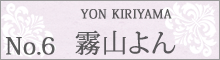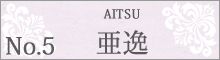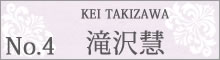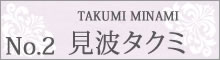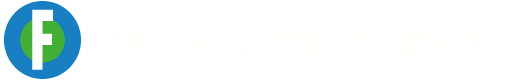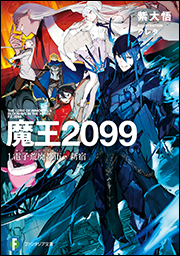第33回ファンタジア大賞《大賞》受賞作『剣と魔王のサイバーパンク』改題『魔王2099』でデビュー。2023年にはアニメ化も発表された。
ファンタジア大賞に初めて投稿する前に書いた文章で一番文字数の多いものは、大学の卒論でした。
今となっては提出した卒論程度の文章量なんかは書けないと話にならないのですが、執筆に至る第一歩は「卒論でたくさん文字書けたからいけるだろ!」というものでした。
そういう些細な事で一歩を踏み出せたから、今の自分があるんじゃないかなーと思っています。ちなみにその最初の作品は一次選考落ちでした。
あ、『魔王2099』、『断頭台の花嫁』発売中でーす。よろしくね。